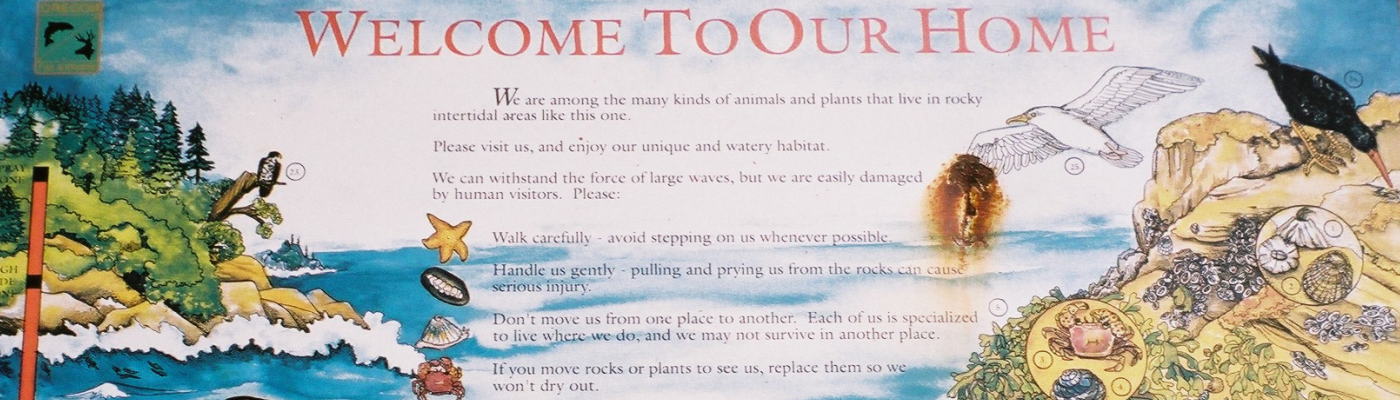昨年(2024年)12月、2度目の救命講習を受講しました。前回の受講時期は思い出せませんが、それほどの年月が経ったこともあり、せっかく学んだはずの救命法も、うろ覚えになってしまっていました。もし緊急事態に遭遇したとき、果たして役立てるのか不安な気持ちがありました。
もし、自宅で家族が突然倒れた場合や、通りすがりに見かけた人が急に倒れたとしたら、その瞬間にどう行動するべきか、焦らずに冷静に救命処置を行える自信がなかったのです。
さて、今回の講習内容は以下の四つでした。
・気道確保の要領
・人口呼吸の方法
・心臓マッサージの方法
・AEDを用いた救命要領

身体で覚える救命法
救命講習はダミー人形を相手に、倒れて意識のない人を目の前にした救命活動を実践します。講師は元東京消防庁の方でした。テキストブックとビデオモニターを見ながら救命法の手順と方法を学ぶわけですが、頭で理解したつもりでもダミー人形を使って実践してみるとなかなかスムーズにいきません。見てわかった気になっても、そんなに甘くはないのです。
講師もそのことはよくわかっているようです。5回、10回と、これでもかと練習を繰り返します。おかげで、カラダの動きのぎこちなさはなくなり、完璧までとはいきませんが、救命の現場でもなんとかお役にたてそうな判断と対応ができるようになったのではないかと自信がつきました。
救命法を忘れないために
とはいっても、普通救命講習を受講して認定書をもらったとしても、1カ月もしないうちに忘れてしまうのは、情けないけれど過去の経験が物語っています。
物忘れも激しくなっています。
講習で支給されたテキストブックは仕舞い込まないで、いつでも開いて救命の方法手順を復習できるように手の届く本棚に入れました。2週間に一度くらいの頻度でページをめくることをルーティンに加えることにしました。